食が心と体を壊す時代に―原点回帰する『命の食事』

「あなたが食べたもので、あなたの体はできている」この言葉は、単なる比喩ではありません。細胞の一つ一つ、脳の神経伝達物質さえも、すべて私たちが口にしたもので構成されています。だからこそ、どんなに医療が進歩しても、「食事」は健康の土台であり続けるのです。
しかし現代に生きる私たちは、この基本を忘れかけています。手軽で美味しい加工食品、安く手に入るファストフード、目を引くコンビニスイーツ。こうした“現代食”は一見、豊かさの象徴のように思えますが、実際には心身に悪影響を与えるものも少なくありません。
実は、私たちの「当たり前」の食生活が、身体的な病気だけでなく、精神疾患をも引き起こしているとしたらどうでしょうか? 今こそ私たちは、原点に立ち返って、「本当に体に良い食事とは何か」を考え直すべきときに来ているのです。
目次
日本の食卓に砂糖が持ち込まれた歴史とその影響

砂糖が日本にもたらされたのは、戦国時代末期。ポルトガル人によって持ち込まれ、当初は「薬」として使われていました。その後、江戸時代に入り、上流階級を中心に嗜好品としての砂糖が広まり、明治維新以降は徐々に一般家庭の食卓にも浸透していきました。
しかし、この「甘さ」の普及とともに、日本人の体質や精神性には徐々に変化が訪れます。もともと、玄米や味噌、野菜中心の食生活をしていた日本人の体は、精製された糖質に対して非常に繊細です。砂糖は、血糖値を急激に上昇・下降させるため、自律神経を乱しやすく、集中力の低下やイライラ、うつ症状を引き起こす原因となり得ます。
戦後、高度経済成長期とともに砂糖の消費量は爆発的に増加しました。昭和30年代には年間1人あたりの砂糖消費量が25kgを超えたとも言われます。そして同時に、精神的な疾患や行動障害を持つ子どもたちの数が増加し始めたのも、この時期からです。
砂糖と精神疾患の関連性

「砂糖が精神に影響を与える」という考えは、かつては一部の研究者や医師の間で語られるにすぎませんでした。しかし現在では、世界中の研究機関が、砂糖の過剰摂取が精神的健康に悪影響を与えることを示すエビデンスを数多く発表しています。
特に注目されているのが、血糖値の急激な変動による影響です。甘いものを食べた直後には一時的に幸せな気分になりますが、それは脳内ホルモンである「ドーパミン」が大量に分泌されるためです。しかし、急激に上がった血糖値はインスリンによって急降下し、その後には「反動」としての倦怠感、イライラ、不安感が襲ってきます。
また、砂糖の過剰摂取は腸内環境を悪化させ、腸内細菌バランスの崩壊を招きます。腸は「第二の脳」とも呼ばれ、幸福ホルモンであるセロトニンの約90%が腸内で作られていることが知られています。つまり、腸が乱れると心も乱れる。現代の「うつ社会」は、実は“腸の不調”が引き金になっている可能性も否定できないのです。
加工食品の罠―便利さの代償としての健康被害

現代の私たちの生活において、「加工食品」はもはや欠かせない存在になっています。冷凍食品、レトルト食品、コンビニ弁当、お菓子、清涼飲料水。これらは時間がない中で手軽に食事を済ませられるという便利さを提供してくれます。
しかし、その便利さの代償として、私たちは「食品の中身」に無関心になってしまったのです。原材料表示を見ると、聞き慣れないカタカナの化学物質がずらりと並び、私たちはそれらを疑うことなく日々口にしています。これらの多くは、保存性や見た目、味の強化を目的に添加されており、栄養価や安全性よりも「売れること」が優先されているのが実情です。
その結果、アレルギー疾患や自己免疫疾患、慢性疲労、発達障害など、現代特有の“見えにくい病気”が増えてきました。加工食品を大量に消費するようになったことで、体内に本来存在しない化学物質が蓄積され、私たちの内臓や神経にじわじわとダメージを与えているのです。
特に注意すべき添加物

加工食品の中で特に注意すべき添加物がいくつか存在します。以下に、代表的な有害添加物について紹介します。
アスパルテーム
「アスパルテーム」Aspartame)は、人工甘味料の一種です。砂糖の約200倍の甘さを持ち、ダイエット食品やゼロカロリー飲料などに広く使われています。
しかしこの物質は、体内でフェニルアラニンやメタノールなどに分解されます。特にメタノールは毒性が強く、視神経への影響や中枢神経障害の懸念が指摘されています。また、頭痛、めまい、不眠、不安感といった症状が報告されており、欧米では神経系への悪影響を問題視する声が多く上がっています。
パラベン酸(パラベン)
「パラベン」は、化粧品だけでなく一部の食品にも使用される防腐剤です。細菌やカビの繁殖を抑える目的で使われていますが、体内に取り込まれた際の安全性は疑問視されています。
研究によっては、パラベンがホルモンのような働きをし、内分泌系に悪影響を及ぼす可能性があるとされています。特にエストロゲン(女性ホルモン)に似た作用があり、乳がんリスクとの関連も指摘されています。長期的な摂取や蓄積がどのような結果をもたらすか、十分に検証されていないにも関わらず、多くの食品や化粧品に当たり前のように含まれているのが現状です。
その他の有害添加物
・グルタミン酸ナトリウム(MSG):旨味を強調するための調味料。過剰摂取で頭痛や吐き気、神経過敏を引き起こすことがある。
・タール色素:お菓子やジュースの鮮やかな色を作るために使われるが、発がん性やアレルギーとの関連が疑われている。
・亜硝酸ナトリウム:ハムやベーコンなどの発色剤。発がん性物質ニトロソアミンを体内で生成する可能性がある。
これらの添加物は、摂取したからといってすぐに病気になるわけではありません。しかし、毎日少しずつ体内に蓄積され、数年、数十年のスパンで体を蝕んでいく可能性があるのです。
“食べてはいけない”現代食品の実例

では、私たちが特に注意すべき「危険な食品」とは何でしょうか。ここでは、一般家庭でもよく見かける食品の中で、実際に健康リスクが高いとされる例をいくつか紹介します。
・ ゼロカロリー飲料・ダイエットコーラ
→ 人工甘味料(アスパルテーム、スクラロース)が多く含まれており、味覚異常や依存性を引き起こす。
・コンビニのおにぎり・パン
→ 保存料、防カビ剤、pH調整剤などが使用されている。見た目は「普通」だが、体内では異物として扱われる。
・ 色鮮やかなキャンディやゼリー
→ タール色素や人工香料が多用されており、子どもの情緒不安定や集中力低下の原因になりうる。
・ベーコンやウインナー
→ 亜硝酸ナトリウムやリン酸塩が含まれ、発がん性や腎機能への負担が懸念される。
・ インスタントラーメン
→ 過剰な食塩、MSG、酸化防止剤などが含まれ、内臓疲労や神経系への悪影響を引き起こす可能性。
これらの食品は「普通にスーパーやコンビニで売られている」ため、安全だと錯覚しがちです。しかし、その“安全神話”は、企業のマーケティングや法的基準によって成り立っているにすぎません。本当の意味での「命を育む食」とは、大量生産された商品とは根本的に異なるのです。
東洋の知恵に学ぶ「食養生」

古来より、東洋医学では「食は命を養うもの」とされてきました。日本でも、江戸時代の医師・石塚左玄は「食養生」という概念を提唱し、「食こそが病の予防であり、治療である」と説きました。さらに中国では「薬食同源(やくしょくどうげん)」という言葉があり、薬と食は本来同じ源から生まれたもの、つまり“食べ物が薬である”という考え方です。
五行思想では、食材は「木・火・土・金・水」に分類され、それぞれが五臓六腑(肝・心・脾・肺・腎)に影響を与えるとされます。たとえば、苦味のある食べ物(火)は心臓に作用し、酸味のあるもの(木)は肝を整えるといった具合です。こうした食材の選び方は、季節や体調、体質に応じて調整され、無理なく自然治癒力を高めていくことが可能です。
現代のように「カロリー」や「栄養素」だけで食を判断する西洋的な視点とは異なり、東洋の食の知恵は「全体性」を大切にし、命を養う視点に立っている点が特徴です。つまり、食べ物は単なるエネルギーではなく、「生命力」そのものであり、調和と陰陽のバランスを通じて体と心を整える手段なのです。
原点回帰のための実践的アドバイス―何を食べ、何を避けるか

私たちが食を通して心身の健康を取り戻すには、難しい理論ではなく、まず「自然なものを自然に食べる」という基本に立ち返ることが大切です。以下に、すぐに取り入れられる実践的な食事の指針を紹介します。
食べるべきもの
・玄米や雑穀米:白米に比べてビタミン・ミネラル・食物繊維が豊富。
・旬野菜と果物:その季節に採れる食材は、体が必要としているもの。
・発酵食品(味噌、納豆、ぬか漬け):腸内環境を整え、免疫力と精神安定に寄与。
・天然出汁(昆布、鰹節):化学調味料ではなく、旨味の本質を味わう。
・自然塩・天然醸造の醤油や味噌:ミネラル豊富で身体に負担が少ない。
避けるべきもの
・人工甘味料(アスパルテームなど):依存性が高く、神経系に悪影響。
・精製された砂糖や白い小麦粉:血糖値の乱高下を引き起こし、精神不安定に。
・保存料、着色料、合成香料が多い加工食品:肝臓や腎臓に過剰な負担をかける。
・ 酸化した油やトランス脂肪酸:動脈硬化、炎症反応、脳機能障害の原因に。
重要なのは、「完璧を目指さないこと」。すべてを急に変えるのではなく、まずは日常の中で「原材料を見る習慣」をつけたり、「一汁一菜」を意識するだけでも、大きな一歩となります。
未来の食文化を見直すために私たちができること

私たちが未来に向けてできることは、「選ぶ」ことです。企業は消費者が何を買うかを見て商品開発を続けていきます。つまり、私たちの選択こそが、これからの食品業界や農業の在り方を形作っていくのです。
・オーガニックや無農薬の野菜を選ぶ
・地元の農家から直接購入する
・信頼できる生協や自然食品店を利用する
・家庭での「手作り」の機会を増やす
・子どもたちに食の大切さを伝える
これらはすべて、小さな行動ですが、積み重ねることで大きな変化になります。食の選択は、社会の価値観や地球環境にもつながっています。だからこそ、「安くて便利」だけで選ぶのではなく、「命を育む」という視点で食と向き合っていく必要があるのです。
おわりに―食べることは生き方そのもの

私たちは、1日に3回、人生の方向を選んでいます。それが「食事」です。どんなに知識を持っていても、どんなに運動をしていても、日々の食が乱れていれば、健康も、精神も、やがて壊れていくでしょう。
逆に、毎日の食卓を見直すことは、人生そのものを立て直すきっかけにもなります。体が変わり、心が整い、思考が明晰になり、生きる力が湧いてくる。その力は薬やサプリメントではなく、「自然の恵み」がもたらすものです。
便利さに頼りすぎた現代の私たちにとって、「原点回帰」は決して後戻りではありません。それは、自然と調和した未来への新しい一歩なのです。
今こそ、もう一度問いましょう。「私は、何を食べて、どう生きていくのか」と。
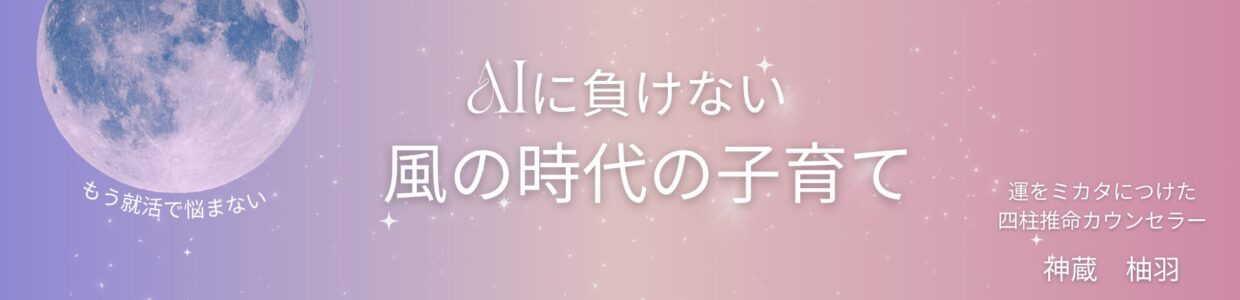







コメントフォーム